2018年04月30日
「少年」たちの宝探し

その場面や音楽や台詞がソラで浮かんでくる。それくらい何度も見た映画「アマデウス」。それを作り出した3人の「少年」たちがこの半年ほどで相次いで亡くなった。
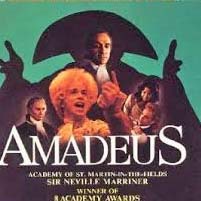
監督のミロス・フォアマンは、チェコ出身のユダヤ人。雪の降る町を泥酔したモーツァルトが歩くシーンは、プラハで撮影されている。大学教授だった父は反ナチ思想の持ち主としてゲシュタポから尋問を受けた後、死亡している。母もアウシュヴィッツで亡くなった。プラハの国立映画学校で学び、東欧世界を代表する映画監督として認知されたが、1968年のチェコの民主化運動「プラハの春」に対するソ連軍の弾圧を機にアメリカに移住。1975年の『カッコーの巣の上で』と1984年の『アマデウス』でアカデミー監督賞を受賞。


『カッコーの巣の上で』。刑務所の強制労働を逃れるために詐病によって精神病院に入院してきたマクマーフィ。しかし精神病院はもっと悲惨な状況にあった。絶対権限を持って君臨する婦長によって運営され、患者たちは無気力な人間にされていたのだ。さまざまな手段で病院側に反抗しようとするマクマーフィに、患者たちも心を少しずつ取り戻し始めた。
決して政治的メッセージではなく、人間の尊厳を軸に管理社会を告発した映画として話題になった。政治家やマスコミの情報操作に踊らされ、巨大企業の消費の的や歯車になり、権力システムに囚われてしまった人々。そんなものを重ね合わせてしまう。

『アマデウス』の重奏低音として流れているのも、そんな「自由な心」なのかもしれない。ミロス・フォアマン。2018年4月13日、自宅のあるアメリカ合衆国コネチカット州にて病没。86歳。翌14日にフォアマンの妻がその死を公表した。

朝日新聞2018年4月30日朝刊から
「アマデウス」、3人の遊び心の結晶 映画監督ミロス・フォアマンを悼む
記憶に残る映画は少なくないが、記憶の中で育ち続ける映画はそう多くない。「アマデウス」(1984年)はそんな映画のひとつだった。
今月半ばに86歳で亡くなった「アマデウス」の監督、ミロス・フォアマンのネット上の訃報記事に、多彩なコメントが寄せられ続けている。「大人になり、ようやくサリエリの葛藤が理解できるようになった」「サリエリが好きだったあのお菓子が食べたい」など、ディテールも鮮やかだ。語りたくなるシーンも、人によって全く異なるらしい。

なぜか。作品のおおもとになったピーター・シェーファーの戯曲は、天衣無縫の天才(モーツァルト)と出会ってしまった秀才(サリエリ)、つまり「個人」の葛藤を克明に暴き出すものだった。それゆえ、誰の胸にもサリエリの悲哀が等しく印象づけられた。しかし映画では、特定の人物に共感を集めてゆく手法をとらず、揺れ動く2人の「関係」にもっぱら焦点を当て続けた。だからこそ、観客は作品に自身の人生や思いを自由に重ね、自分だけの感動をはぐくむことができた。

2015年11月、選曲と演奏を担当した世界的指揮者のネビル・マリナーに、インタビューの合間に「アマデウス」制作の経緯を尋ねたら、いたずらっ子のような声色で昔語りを始めた。
「この仕事が決まって最初にやったことが、ミロスとピーターを僕の田舎の自宅に招くことだった。飽きるほど徹底的に遊んだよ。テニスをしながら、酒を飲みながら、あの曲いいね、この曲使えないかな、って。みんな、モーツァルトと人生が大好きだった」
「ミロスもピーターも僕に、つまり音楽に、すべて従うと誓ってくれた。この映画では、ストーリーより音楽が優先するのだと」

モーツァルトをキンキン声で罵倒する義母の口が、オペラ「魔笛」で超絶技巧をきかせる夜の女王の口にオーバーラップしてゆくなどのアイデアは、そうした「遊び」のるつぼから生まれたものだった。多様なイメージを喚起する音楽の力にすべてを預けたフォアマンの映像、シェーファーの言葉、そしてマリナーの演奏。この3人の芸術家のピュアな遊び心が起こした化学反応の産物こそが、「アマデウス」だったのだ。
音楽学者の岡田暁生さんは「『アマデウス』を境に、クラシックのアイコンはベートーベン(父権の象徴)からモーツァルト(永遠の子供)になった」と指摘する。映画のモーツァルトのあのけたたましい笑い声が、歴史的なパラダイム転換を引き起こし、高みに鎮座する芸術が今の時代を生きる私たちの手の中にすとんと落ちてきたのだと。
先のインタビューの7カ月後、シェーファー死去。同じ年の10月にはマリナーも。そして今月、フォアマンが逝った。マリナーが名付けた「3人の『少年』の宝探し」は、永遠に終わりを告げた。
しかし「アマデウス」はこれからも、権威に頼らず、己の視点で芸術について語る自由の尊さを思い起こさせてくれるだろう。作家個人の思いを超えた普遍性と、それがはぐくむ多様性。これこそが、芸術作品が「古典」として永遠のいのちを携えるための、必要不可欠な条件なのだと。(吉田純子)
Posted by biwap at 09:50
│芸術と人間




