 › 近江大好きbiwap › 2018年02月
› 近江大好きbiwap › 2018年02月2018年02月20日
何を待つのか太公望
とりあえずの中国史・その3

周の領主・文王。渭水のほとりで釣りをしていた老人に出会う。老人の名は呂尚。殷王を倒すため、いつか誰かが自分を求めてくる。80才になるまで静かに魚釣りをしながら待った。
周を助ける賢人が現れる。そう聞かされて来た文王。「この男こそ祖父が待ち焦がれていた男に違いない」と感じた。文王は呂尚を連れ帰り、大臣に任じ「太公望」の称号を与えた。「太公望」とは、文王の祖父「太公」が待ち「望」んでいた男という意味。
文王の死後、その子・武王の参謀となった太公望・呂尚。戦いの先頭に立ち、殷を「牧野の戦い」で打ち破った。軍功により封ぜられた土地を呂尚は「斉」と名付けた。斉は太公望の統治下、魚や塩資源をもとに国土開発や交易を行い繁栄したという。

ところで、太公望が周に仕官する前のこと。仕事もせずに本ばかり読んでいた太公望は妻に愛想をつかされ離縁された。ところが太公望が周から斉に封ぜられ出世するや、女は太公望に復縁を申し出た。太公望は水の入った盆を持ってきて水を床にこぼし、「この水を盆の上に戻してみよ」と言った。これが「覆水盆に返らず」の故事である。

殷を攻めようとした武王だが、「殷は周の主君。主君を討つのは道義に反する」という声が起こる。権力奪取には、その正当性が求められる。武王はこう反論した。「天子は天帝の命によりその地位にある。しかるに、その暴虐に人心は離れ、殷の紂王はすでに天命を失っている」
「万世一系の天皇」に革命を起こすことはできない。しかし、現実主義の中国では天命が革(アラタ)まると、天子の姓は替えられる(易姓革命)。では天命はどこに現れるのか。「天に口無し人を以て言わしむ(天声人語)」。革命により、殷から周への政権交代が起こった。
殷周革命の舞台となった周。もともと殷の西方陝西省「岐山」の麓にいた民族だった。織田信長は、美濃の稲葉山城を攻略し、そこを自らの本拠地とし「岐阜」と改名している。これは岐山の麓で興り、後に天下を治めた周王朝の故事に倣ったものである。彼は革命を模倣しようとしたのか。

周が都をおいたのが鎬京(コウケイ)。今の西安あたり。周王は、有力氏族の首長に邑を与える。未開の土地に新たな邑を建設させてそこの統治をまかせた。配下の邑をつくることで全土ににらみを利かした。周王から邑の支配をまかされた者を諸侯といい、諸侯は周王に対して軍役と貢納の義務を負った。これを「封建制」という。
しかし、西欧の封建制と違うのは、契約関係ではなく擬似血縁関係だったということ。周の王様は本家、諸侯は分家。本家が祖先の霊を祭ることで、周ファミリーの秩序は保たれる。後の乱世の時代に儒学が依拠しようとしたのは、この「秩序」だったのだろう。

周の時代は大きく二つに分かれる。前半を西周(前1027~前771)、後半を東周(前770~前256)という。前半の都が鎬京、後半の都が洛邑(ラクユウ)。都が東に移ったので東周というのだが、それにはこんないきさつが。
都が移ったときの王が幽王。その妃・褒姒(ホウジ)は絶世の美人だが、一つだけ変わったところがあった。生まれてから一度も笑ったことがない。そんなある時、西方から異民族が鎬京を襲撃してきた。幽王は救援の烽火(ノロシ)を上げた。諸将がさっそく駆けつけたが、何ごともなかった。右往左往する様子を見た褒姒は、はじめて晴れやかに笑った。喜んだ幽王は、そののちたびたび烽火を上げさせたので、次第に諸将は烽火の合図を信用しなくなった。やがて、本当に異民族が鎬京に攻め込んできた。幽王は必死に烽火をあげるが、諸侯は誰一人として救援に来なかった。そのまま、鎬京は陥落して周は都を東の洛邑に移したというわけ。
殷の妲己(ダッキ)といい周の褒姒(ホウジ)といい、古代中国史には美貌によって王君を破滅させ国を滅亡に追いこむ魔性の女性がしばしば現れる。これを「傾国傾城(ケイセイ)」という。歴史には「傾城の美女」が続々登場することになる。しかし、これは「男の偏見」史観かもしれないので、ご用心。

周の領主・文王。渭水のほとりで釣りをしていた老人に出会う。老人の名は呂尚。殷王を倒すため、いつか誰かが自分を求めてくる。80才になるまで静かに魚釣りをしながら待った。
周を助ける賢人が現れる。そう聞かされて来た文王。「この男こそ祖父が待ち焦がれていた男に違いない」と感じた。文王は呂尚を連れ帰り、大臣に任じ「太公望」の称号を与えた。「太公望」とは、文王の祖父「太公」が待ち「望」んでいた男という意味。
文王の死後、その子・武王の参謀となった太公望・呂尚。戦いの先頭に立ち、殷を「牧野の戦い」で打ち破った。軍功により封ぜられた土地を呂尚は「斉」と名付けた。斉は太公望の統治下、魚や塩資源をもとに国土開発や交易を行い繁栄したという。

ところで、太公望が周に仕官する前のこと。仕事もせずに本ばかり読んでいた太公望は妻に愛想をつかされ離縁された。ところが太公望が周から斉に封ぜられ出世するや、女は太公望に復縁を申し出た。太公望は水の入った盆を持ってきて水を床にこぼし、「この水を盆の上に戻してみよ」と言った。これが「覆水盆に返らず」の故事である。

殷を攻めようとした武王だが、「殷は周の主君。主君を討つのは道義に反する」という声が起こる。権力奪取には、その正当性が求められる。武王はこう反論した。「天子は天帝の命によりその地位にある。しかるに、その暴虐に人心は離れ、殷の紂王はすでに天命を失っている」
「万世一系の天皇」に革命を起こすことはできない。しかし、現実主義の中国では天命が革(アラタ)まると、天子の姓は替えられる(易姓革命)。では天命はどこに現れるのか。「天に口無し人を以て言わしむ(天声人語)」。革命により、殷から周への政権交代が起こった。
殷周革命の舞台となった周。もともと殷の西方陝西省「岐山」の麓にいた民族だった。織田信長は、美濃の稲葉山城を攻略し、そこを自らの本拠地とし「岐阜」と改名している。これは岐山の麓で興り、後に天下を治めた周王朝の故事に倣ったものである。彼は革命を模倣しようとしたのか。

周が都をおいたのが鎬京(コウケイ)。今の西安あたり。周王は、有力氏族の首長に邑を与える。未開の土地に新たな邑を建設させてそこの統治をまかせた。配下の邑をつくることで全土ににらみを利かした。周王から邑の支配をまかされた者を諸侯といい、諸侯は周王に対して軍役と貢納の義務を負った。これを「封建制」という。
しかし、西欧の封建制と違うのは、契約関係ではなく擬似血縁関係だったということ。周の王様は本家、諸侯は分家。本家が祖先の霊を祭ることで、周ファミリーの秩序は保たれる。後の乱世の時代に儒学が依拠しようとしたのは、この「秩序」だったのだろう。

周の時代は大きく二つに分かれる。前半を西周(前1027~前771)、後半を東周(前770~前256)という。前半の都が鎬京、後半の都が洛邑(ラクユウ)。都が東に移ったので東周というのだが、それにはこんないきさつが。
都が移ったときの王が幽王。その妃・褒姒(ホウジ)は絶世の美人だが、一つだけ変わったところがあった。生まれてから一度も笑ったことがない。そんなある時、西方から異民族が鎬京を襲撃してきた。幽王は救援の烽火(ノロシ)を上げた。諸将がさっそく駆けつけたが、何ごともなかった。右往左往する様子を見た褒姒は、はじめて晴れやかに笑った。喜んだ幽王は、そののちたびたび烽火を上げさせたので、次第に諸将は烽火の合図を信用しなくなった。やがて、本当に異民族が鎬京に攻め込んできた。幽王は必死に烽火をあげるが、諸侯は誰一人として救援に来なかった。そのまま、鎬京は陥落して周は都を東の洛邑に移したというわけ。
殷の妲己(ダッキ)といい周の褒姒(ホウジ)といい、古代中国史には美貌によって王君を破滅させ国を滅亡に追いこむ魔性の女性がしばしば現れる。これを「傾国傾城(ケイセイ)」という。歴史には「傾城の美女」が続々登場することになる。しかし、これは「男の偏見」史観かもしれないので、ご用心。
2018年02月16日
夢は世界平和

『綾瀬はるか、夢は世界平和、壮大過ぎる願いに周囲があ然』
女優の綾瀬はるかが10日、都内で行われた映画『今夜、ロマンス劇場で』の公開初日舞台あいさつに登壇。映画にかけてかなえたい夢を問われると「世界平和です」ときっぱり。突拍子もない夢に周囲はあ然としていた。(中略)
また、映画にかけて実現させたい夢を語ることに。通常のイベントでは出演陣が無難に答えることが多いが、やはり綾瀬は綾瀬だった。「オリンピックも開催中ですし」と話し始めると「世界平和です」ときっぱり。理由については「みなさんが、いつも笑顔で健やかに過ごせる、そんな世の中がいいです」と笑顔を見せた。
あ然としたのは共演陣だ。壮大過ぎる願いの後を受けた坂口は「世界平和の後ですもんね…」と閉口。「やっぱり、この作品の大ヒット」と“お約束”で無難に回避し、綾瀬は「ごめんなさい…」と苦笑いを浮かべた。【毎日新聞(ORICON NEWS) 2018.2.10.】

綾瀬はるかさんが、映画の舞台挨拶でコメントした「夢は世界平和」。それを面白おかしく扱っている現状に違和感を持った人も多いようだ。
「制裁のための制裁」は、結局のところ一番弱い人たちにひずみを押しつけている。漂流した漁船の死体を見て、制裁の効果が表れた結果だと平然と言ってのける。この国の感性はどうにかなってしまっている。
だからこそ、声を上げた人を見殺しにしてはいけない。みんながみんな同じ方向を向いているわけでは決してないのだ。

「ゆるねっとにゅーす」のつぶやきから
ボク自身、彼女がここまで色々なことを考え、日本や世界の現状に危機感を持っていたことが分かって本当に嬉しいし、孤軍奮闘している吉永小百合さんに続く頼もしい若い存在が出てきてくれたね。
こうして、公の場で、世界の平和や世の中の人々の健やかな暮らしを願いつつ、自分自身の考えをしっかりと話すことが出来るのはとても素晴らしいし、その一方で、「ボクの夢も世界平和です!」「みんなで世界平和を願いましょう」という流れにはならず、結局はいつもの調子で制作会社や社会の空気に忖度しつつ、狭小で内輪的な世界観のコメントに終始してしまったのは残念だったね。
そして、彼女が「ごめんなさい」と謝るような空気になってしまったのも、同調圧力のようなイヤなものを感じる。「あ然」などと若干茶化すような論調になっていて、確かに、動画を観ると共演者もやや困っているような様子が見られる。
こういう危うい時勢だからこそ、「戦争はいやだ」「日本や世界を平和に」と民衆が声を上げることはとても大事だし、庶民が戦争に反対したり平和を求めることは、戦争を引き起こすことで多大な金儲けをしている軍産資本のグローバリストにとって「大きな脅威」であり都合の悪いことなんだ。
NHKも北朝鮮危機を派手に煽り、いよいよ戦争プロパガンダのような報道も始めてきている中で、こういう今こそ、国民は感性を研ぎ澄まして、彼女のように「平和」を訴えたり、「戦争は嫌だ」という世論を大きく作っていく必要があるし、どうも、最近の日本では、「平和」を願ったり「戦争はイヤだ」との声を出すことそのものが、奇異な視線を浴びたり「風変わりな人」とのイメージが作られつつあるような空気も感じる。

「AERA dot.」元SEALDs諏訪原健さんの記事から
なぜこの社会では、平和を求める語りが、馬鹿げたもののように扱われるのだろうか。2月10日にオリコンが配信した記事で「綾瀬はるか、夢は『世界平和』 壮大過ぎる願いに周囲があ然」と題したものがあった。記事の中では、実現させたい夢として「世界平和」を挙げた女優・綾瀬はるかの発言が、突拍子のない発言のように扱われていた。彼女の真摯な発言を、ある種の笑い話にするような論調は、読んでいて不快だった。
自分も特定秘密保護法や安保法制など、平和を遠ざけるような政治の動きに対して、声を上げてきたが、その度に、そのような行動を冷笑するような言葉を浴びせられてきた。平和という理想を語ることは、頭の中が「お花畑」であるかのようにあざ笑う人々が、この社会には数多くいる。先ほど挙げた記事の論調には、この社会の「平和」に対する空気が反映されているように感じる。
北朝鮮情勢に対するこの社会の人々の認識にも、そのような風潮を見ることができる。2月13日に発表されたNHKの世論調査では、「五輪での南北融和の動き」に対して、「大いに評価する」が5%、「ある程度評価する」が21%なのに対して、「あまり評価しない」が37%、「まったく評価しない」が28%だった。この社会においては、融和に向けた動きは否定的に捉えられているというのが現状だ。
このような状況は、北朝鮮情勢をめぐる日本政府の対応を後押ししているように思う。2月9日に行われた日韓首脳会談の中で、安倍首相は、米韓合同軍事演習を冬季五輪後に予定通り実施するよう求め、「北朝鮮のほほ笑み外交に目を奪われてはならない。対話のための対話では意味がない」などと文在寅大統領をけん制した。それに対して、文大統領は、演習の実施は内政の問題だとして不快感を示すとともに、日本政府が対話に向けて動き出すことを願うと語っていた。
北朝鮮と韓国、そしてアメリカの動きを見ていくと、このような日本政府の対応には違和感を覚える。2月10日、北朝鮮の金与正氏は、文大統領に対して、南北関係の改善への意志を示した親書を手渡すとともに、大統領の訪朝を求めた。文大統領は、米朝の早期の対話が必要だとの認識を示しつつも、訪朝に向けた環境を整えていく意志を表明した。アメリカのペンス副大統領も、北朝鮮に対する厳しい姿勢を崩してはいないが、北朝鮮が望めば対話を行う可能性を示唆している。
そのような対話に向けた動きが進もうとする中で、「対話のための対話には意味がない」として、一貫して強硬な姿勢を貫いている日本政府は、国際社会の動向から取り残されているのではないかと思う。「朝日新聞 映像報道部」のTwitterアカウントが、2月9日に投稿した写真には、それが象徴されているようだった。平昌オリンピックの開会式で、手を取り合う金与正氏と文在寅大統領。そしてそれには目もくれず、ひとり遠くを見つめる安倍首相。日本政府は、南北関係の融和に向けた動きを、真摯に受け止めるべきではないだろうか。
さらに言えば、政府に加担しているかのような一部報道もある。NHKニュースの公式Twitterは、「北朝鮮の狙いが、米韓同盟の分断にあるのは間違いありません」と南北融和の動きに否定的な見解を示した。2月11日の毎日新聞の社説は、「北朝鮮が文氏に会談提案 平和攻勢に惑わされるな」と題して、「南北の首脳会談を必要としているのは北朝鮮である。そこを見誤ると、核を温存したまま国際包囲網を突破しようとする北朝鮮に手を貸すことになってしまう」としており、「対話のための対話には意味がない」という政府の姿勢とつながるような見解を示している。
私には、このままでは日本社会が、南北の対立を深めることに手を貸してしまうのではないかと思えてならない。そうならないために、大切な事は、私たち自身が、この東アジアに何を求めるのかをきちんと考え、表明することのように思う。私たちには、政府に態度を改めるように迫るだけの力があるはずだ。
政府の高官になったような気持ちで、北朝鮮には圧力をかけなければならないなどと、平和に向けた取り組みを一蹴するのは簡単なことだ。しかし軍事的な対立にまで至れば、苦しむのは私たちと同じ一介の民衆ではないのか。あるいは戦火が広がれば、私たち自身も無関係ではいられないのではないか。そんなことに加担してはいけない。
朴槿恵大統領(当時)の弾劾訴追案が可決された2016年12月9日、私はソウルにいた。その時、現地の人々は歓喜しているというよりも、むしろこれからの韓国社会がどうなるのかということに憂慮していた。ある人は、今後の懸念として、「韓国では、政治家が北朝鮮に対して融和的な態度をとれば、北朝鮮のスパイなどと非難される。韓国では進歩主義的な政治家であっても、強行的な姿勢をとることを求められる。今後どんな人がトップになるのかが重要だ」と語っていた。
その言葉を聞いていたからこそ、文大統領が、南北融和に向けた取り組みを進めていることは、本当に尊いことだと、私は受け止めている。彼の行動を、あるいは彼を大統領に押し上げた韓国社会の人々の意志を、無下にするようなことはしてはいけないと思う。対話から生まれる平和の可能性にも、私たちは目を向けるべきでないだろうか。
2018年02月13日
微笑み返し



トランプ氏と金正恩氏のそっくりさんが平昌に登場し騒然!報道席からは追い出されてしまうも、観客席や街中では周りの人とハイタッチ! どうせやるなら、これくらいカラッとやらなくちゃ。
一方、陰湿な某国においては、「微笑み戦略に屈服した土下座外交」と友好ムードに苦々しい顔。クギを刺しに行ったはずの100%服従の某国首相は、そっくりそのまま微笑み返しされそうだ。
自分の行動を客観視できなくなってしまうのは、相当に重症である。メディアが同じ口調で煽動するのは、相当に危険である。
テレビを見ていて、あの人がこんなことを言うのかと、失望させられることが少なくなかった。逆に、あの人がこんなことを言うのかと感動したこともあった。言葉の一つ一つの重みを、こんな時代だからこそ感じてしまう。
歴史学者・羽仁五郎の「真理は少数にあり」という言葉を思い出す。迎合している人間は、結局誰からも信頼されない。異を唱えることに誇りを持って、過剰同調社会の閉塞状況を「微笑み返し」で明るく切り返そう。
成程と思ったLITERAXの記事を以下引用。

ネトウヨや保守メディアはもちろん、ワイドショーまでが連日、底意地の悪いバッシングを繰り広げている平昌五輪。だが、日本からの「失敗しろ」コールも虚しく、一昨日の開会式は大きな盛り上がりをみせ、世界中に感動を与えた。
韓国と北朝鮮の合同チームによる統一旗をかかげての入場、南北の女子アイスホッケー選手が2人で聖火を運び、最終ランナーであるキム・ヨナへとつないだ聖火リレーはもちろんだが、中盤のショーも人種や民族を超えた融和、世界平和への強い思いを込めた素晴らしいものだった。
韓国で平和な時代にしか現れないとされる「人面鳥」を登場させ、ジョン・レノンのイマジンを歌い上げながら、キャンドルで平和の象徴である鳩をかたちづくっていくクライマックス。朝鮮半島がいまも一触即発の状態にあるなかで、こうしたメッセージを発信したことは非常に大きな意味がある。

しかも、これらのショーは平和を希求する姿勢や韓国の伝統文化を表現しつつも、言語や国籍の壁を越え、誰もが愉しめるエンタテインメントとして成立していた。
これはおそらく、開会式の総合監督のソン・スンファン(宋承桓)、総合演出・のヤン・ジョンウン(梁正雄)コンビの手腕によるところが大きいだろう。
周知のように宋承桓は、韓国の伝統的なリズム「サムルノリ」をベースに、包丁やまな板などのキッチン道具を楽器として用いたミュージカル『NANTA』を生み出したことで知られる芸術監督。その言語の壁を超えてたのしめるパフォーマンスは韓国で史上最多の観客動員数を記録しただけでなく、日本をはじめアメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア、中国、オーストラリアなど世界各国で公演を成功させ、ブロードウェイにも進出するなど、国際的な評価を得てきた。
一方、ヤン・ジョンウン(梁正雄)も韓国で人気の演出家だが、日本やスペインなどでも演劇活動をした経験があり、2008年には、韓国の複合芸術センター・芸術の殿堂と日本の新国立劇場が共同で制作した『焼肉ドラゴン』を、在日韓国人の作者・鄭義信と共同演出。演劇賞を総なめにしたことで知られている。
民族主義、ナショナリズムが強いといわれる韓国だが、開会式はけっして“内向き”でなく、歴史への深い造詣をもちながら世界に通用するクリエイターをきちんと見極めて起用したことが、成功につながったといえるだろう。

しかし、一方の日本はどうだろう。この状況で韓国側に「五輪が終わったら米韓軍事演習を実施しろ」と迫った安倍首相。韓国の歴史をふりかえるパートで、「外国からの度重なる侵略など苦難にさらされてきた韓国」とまるで他人事のように解説したNHKの中継。そのNHKを「反日」と攻撃し、プロジェクションマッピングを使っていたというだけで「リオ五輪閉会式の東京のプレゼンテーションのパクリだ」とがなりたてるネトウヨ…それこそ日本のことしか考えず、日本でしか通用しない主張をがなりたてる内向きなグロテスクさには辟易とさせられる。
さらにもうひとつ、この開会式を見ていて、改めて不安になったのが、2020年の東京五輪のことだ。昨年末、東京五輪の開会式・閉会式の演出チームが発表されたが、リオ五輪にひき続きの椎名林檎らに加え、山崎貴、川村元気、野村萬斎というなんともドメスティックな顔ぶれ。しかも、産経新聞などによると、構成とストーリーはあの山崎貴が担当するというのだ。
山崎貴といっても、普通の人はピンとこないだろうが、映画『永遠の0』や『ALWAYS 三丁目の夕日』の監督。作品はいずれもヒットしているが、映画監督としての評価は「CGの使い方がうまいだけで、演出は凡庸だし、物語のつくりかたも陳腐。まあそれが気楽に観れて、大衆受けする理由かもしれませんが」(映画評論家)と、けっして高くない。
当然、海外の知名度もほとんどない。アメリカでもヨーロッパでもアジアでもいいが、海外の劇場の前で映画ファンに「タカシヤマザキって知ってる?」と聞いてみたらいい。かけてもいいが、ほとんどの人は「だれ、それ」と答えるはずだ。
五輪の開会式・閉会式といえば、たとえば北京ではチャン・イーモウ、ロンドンではダニー・ボイル、リオではフェルナンド・メイレレスが、それぞれ演出を務めた。国際的な映画賞を受賞するなど世界的な評価も知名度も高く、日本人でも知っている監督ばかりだ。
冬季は夏季ほどビッグネームではないが、それでも、今回の平昌のように、世界に通用するということを意識して演出家を選んでいる。

それに比べて、東京五輪はこんな国際性のない内向きの人選でいいのか。『紅いコーリャン』『トレインスポッティング』『シティ・オブ・ゴッド』ときて、『永遠の0』。『初恋のきた道』『スラムドッグ$ミリオネア』『ブラインドネス』だったのに、『ALWAYS 三丁目の夕日』、これで本当に恥ずかしくないのか。
いや、国際性がないどころの話ではない。山崎は周知のように、あの百田尚樹原作の特攻礼賛愛国ポルノ映画『永遠の0』を監督した人物なのだ。いまはまだ話題になっていないが、東京五輪が近づいてもしその事実が知れ渡ったら、世界中の顰蹙を買う可能性だってある。
実際、少し前、南九州市が神風特攻隊を世界遺産に申請しようとした際、「日本は世界的には“狂った自爆行為”ととられている“神風特攻隊”を“国に命をささげた英雄”としている」と海外メディアから批判された。“特攻”を美化する映画の監督が、世界的イベントであるオリンピックの開会式・閉会式の演出を務めるなど、どう考えても正気の沙汰ではないだろう。
こういうと、「山崎監督には政治性はない。『永遠の0』も原作やテレビドラマ版にあった攻撃的な描写や政治的主張はすべてカット。誰もが感動できるエンタテインメント作品に仕上げていた」などという反論が返ってくるが、山崎作品はむしろヤバい部分や政治的な部分を脱臭しているからこそ問題なのだ。思想的偏向が前面に出ている百田尚樹よりもひろがりがあるぶん、悪質といえるかもしれない。
この“脱臭することの悪質さ”という山崎作品の特徴は出世作『ALWAYS三丁目の夕日』にも共通している。
同作は昭和30年代を徹底して「貧しくても、夢や希望に満ち溢れていた」「人と人の絆が深く、あたたかい人情に溢れていた」時代として描き、知らない若い世代に「日本の古き良き時代」として郷愁を感じさせる仕掛けになっている。
しかし、それは昭和30年代の本当の姿ではまったくない。この時代にあった、貧富の凄まじい格差や公害、犯罪率の高さ、麻薬の蔓延、むき出しの差別……そういった負の部分を全てスルーし、ファンタジーのように描いているだけなのだ。そういう意味では、『ALWAYS 三丁目の夕日』も、『永遠の0』と同じく本質は“日本スゴイ”の愛国ポルノでしかない。
実は、この『ALWAYS三丁目の夕日』の欺瞞性に怒り、そのアンチテーゼというべき作品をつくった人物がいる。その人物とは、先に紹介した平昌五輪の総合演出担当・梁正雄が演出した日韓共同制作の演劇『焼肉ドラゴン』の作者で、『月はどっちに出ている』『血と骨』などの映画脚本でも知られる在日韓国人の劇作家・鄭義信。そして、『ALWAYS三丁目の夕日』のアンチテーゼとして生み出されたのは、まさに、鄭と平昌五輪の総合演出担当・梁が共同演出した『焼肉ドラゴン』だった。
鄭は『焼肉ドラゴン』を公演するにあたって、そのコンセプトをこう説明していた。
「あの時代が美化されているが、そんなに美しいものではなかった。僕は一人だけでも“裏ALWAYS”をやりたい。在日を通じて日本の一つの裏社会、歴史の断片を感じてもらえればうれしい」(東京新聞)
「いわば、逆『ALWAYS 三丁目の夕日』の世界。暮らしが豊かになる裏で、僕より下の4世、5世には、自身が在日という実感すら持てない環境で育った人もいる。かつてこんな文化があったことを、どうしても書き留めておきたかった」(朝日新聞)

この『焼肉ドラゴン』は先日、真木よう子・井上真央・桜庭みなみ・大泉洋というキャストで、作者である鄭義信の監督で映画化されることが発表されたが、その内容は鄭のいうとおり、逆『ALWAYS 三丁目の夕日』というべき作品だ。
舞台は、大阪万博に向け急ピッチで開発が進み始めた時代の関西の地方都市。主人公は在日韓国人集落で小さな焼肉店を営む在日韓国人の一家。しかし、集落は立ち退きを迫られてしまう。コミュニティの崩壊によって、アイデンティティを失っていく人々…。そこには、『ALWAYS 三丁目の夕日』がスルーした、そして高度成長期の日本が隠そうとした、残酷な本質が描かれている。
しかし、こうしたアンチテーゼ的作品が生まれ、高い評価を受けたというのは、逆にいうと、『ALWAYS 三丁目の夕日』が、過去の日本をファンタジー化する過程で、いかにマイノリティを排除し、差別性を内包していたかの証明でもある。
そう考えると、山崎貴に東京五輪の総合演出をやらせるリスクは、特攻賛美映画の監督だったという経歴だけではない。それこそ、人種や民族、文化の多様性を最も尊重しなければならないオリンピックの開会式で、新たにこういう無自覚な差別をまきちらす可能性さえあるだろう。
それにしても、いったいなぜ、こんな映画監督をよりにもよって、世界中から注目される祭典の演出責任者に選んだのか。日本に国際的な評価を獲得しているクリエイターがいないわけではない。ぱっと思いつくだけでも、宮崎駿、塚本晋也、坂本龍一、北野武…少なくとも、山崎貴のように「それ誰?」ってことにはならない映画監督や劇作家はけっこういるはずだ。
そこで思い出されるのが、安倍首相が山崎監督の映画を大のお気に入りだという事実だ。安倍首相は著書『美しい国へ』(文春新書)のなかで、『ALWAYS 三丁目の夕日』について「いまの時代に忘れられがちな家族の情愛や、人と人とのあたたかいつながりが、世代を超え、時代を超えて見るものに訴えかけてきた」「昭和30年代の日本では、多くの国民が貧しかったが、努力すれば豊かになれることを知っていた。だから希望がもてた」などと絶賛していた。
『永遠の0』についても、原作を愛読書としてたびたび大絶賛しているだけでなく、映画館にも足を運び「感動しました」と感極まってみせた。最近も山崎監督の新作である『DESTINY鎌倉物語』を観に行ったことがニュースになっていた。
たしかに、山崎監督のペラペラな作風は「映画好き」を公言するわりに映画的教養がまったく感じられない安倍首相が好みそうではある。
しかも、取り上げるテーマも、安倍首相大好きなものばかりだ。先の戦争と特攻を美化する『永遠のゼロ』は言うに及ばず、『ALWAYS 三丁目の夕日』が美化した昭和33年も、安倍の祖父である岸信介が総理だった時代である。安倍首相にとって、山崎貴は、偉大なおじいちゃんとおじいちゃんを愛する自分を全面肯定してくれる監督なのだ。
だからといって、安倍首相が直接、「山崎監督がいい」と圧力をかけたかどうかはわからないが、しかし、いまの東京五輪組織委員会やその周辺にいる官僚たちの様子を見る限り、“世界に通用するかいなか”よりも“安倍首相の趣味”を忖度して、人選をした可能性は十分あるだろう。

いずれにしても、この人選やリオ五輪閉会式での日の丸を多用した演出、“安倍マリオ”を見ていると、東京五輪の開会式ではもっとグロテスクな愛国ポルノショーを世界にさらすことになるのではないか。今から恐ろしくてしかたない。

2018年02月12日
酒池肉林コード
とりあえずの中国史・その2

夏王朝滅亡後、あとを継いだのが殷(イン)王朝。考古学上、確実に証明できるのはここからである。殷というのはあとから付けた名前で、当時は商(ショウ)と呼んでいた。商の時代が紀元前16世紀頃から紀元前11世紀頃まで続く。

殷はもともと邑(ムラ)の一つだった。他の邑に比べて規模が大きく、軍事的にも強力だったため、周辺の邑を傘下に収めて連合体を形成していった。この連合体が殷王朝。


殷の遺跡が殷墟(インキョ)。王の墓が発掘されている。逆ピラミッド型に掘った頂点に王の遺体が埋葬。王の棺の下に埋められている犬はあの世への案内役。王以外にもたくさんの殉死者が埋葬。青銅製の酒器もたくさん並べてある。あの世で王を守るための兵士。戦車もある。
死んだ人の霊はそのまま神になって存在し続けているという祖霊崇拝は、朝鮮半島や日本にも伝わり東アジアの宗教的伝統となっていく。それにしても、神への生け贄か、魔除けなのか、おびただしい数の生首や殉死者は、権力の集中と大きさをうかがわせるものである。


殷代の青銅器。一面に刻まれたグニャグニャの模様。原型は羊の怪獣なのか、蛇のお化けなのか、逆巻く黄河の水なのか。魑魅魍魎がうじゃうじゃいた当時の人たちの精神世界を表しているようである。神々や悪霊や妖怪が満ち溢れたこの宇宙。

殷の政治の特徴は祭政一致の神権政治。殷王が占いに使ったのが動物の肩甲骨や亀の甲羅。甲骨の亀裂から神意を読み取り吉凶を判断するのが殷王の役割だった。占った結果を甲羅や骨の裏側に刻んで記録した。これが甲骨文字。漢字の原型となる。
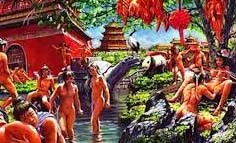
殷の最後の王が紂王(チュウオウ)。絶世の美女と言われた妃・妲己(ダッキ)の虜となり、彼女を喜ばす為に淫蕩な世界に溺れて行った。妲己の為に離宮が造られ、大きな池に酒を満たし、木々には肉が吊るされた。淫らな歌謡が辺りに流れる中、一糸まとわぬ男女が酒の池で戯れ、肉の林で遊ぶ。これが「酒池肉林」。さらに彼女は、人々が本気で殺し合う様を見ては喜び、人民に怨嗟の声が広がると、炮烙(ホウラク)の刑が考え出された。油を塗った柱の上に囚人を上がらせ、下から火を焚きつけるという刑。心ある重臣は王の行状を諌めたが、諫言した者は惨殺され、千肉にされた。
やがて、諫言に寄って捕らえられていた殷王の補佐役・西伯の死後、その息子である周の武王が殷に攻め寄せた。しかし、すでに紂王を見限っていた殷の兵士に戦意はなく、王は宮殿に火を放ち殷王朝は滅んだ。武王は妲己を捕らえて首を刎ね、「殷を滅ぼしたのはこの女だ!」と晒し者にしたという。
実に凄まじい話だが、政権奪取した側がその正当性を示すために前政権の残虐性を脚色することはよくあることだ。『日本書紀』に出てくる第25代・武烈(ブレツ)天皇も凄まじい悪行が並べたてられている。「人の生爪を剥して山芋を掘らせる、人を登らせた木を倒して登った人を殺す、池の樋から人を流して矛で刺殺する、人を木に登らせて弓で射殺する、女性を裸にして目の前で馬の交尾を見せる」。
この武烈の後に、応神天皇5世の孫として越前から入ったのが継体天皇である。王朝交替の歴史観が現れているとの説もある。この「酒池肉林」コード、いかに読み解くべきなのか。

夏王朝滅亡後、あとを継いだのが殷(イン)王朝。考古学上、確実に証明できるのはここからである。殷というのはあとから付けた名前で、当時は商(ショウ)と呼んでいた。商の時代が紀元前16世紀頃から紀元前11世紀頃まで続く。

殷はもともと邑(ムラ)の一つだった。他の邑に比べて規模が大きく、軍事的にも強力だったため、周辺の邑を傘下に収めて連合体を形成していった。この連合体が殷王朝。


殷の遺跡が殷墟(インキョ)。王の墓が発掘されている。逆ピラミッド型に掘った頂点に王の遺体が埋葬。王の棺の下に埋められている犬はあの世への案内役。王以外にもたくさんの殉死者が埋葬。青銅製の酒器もたくさん並べてある。あの世で王を守るための兵士。戦車もある。
死んだ人の霊はそのまま神になって存在し続けているという祖霊崇拝は、朝鮮半島や日本にも伝わり東アジアの宗教的伝統となっていく。それにしても、神への生け贄か、魔除けなのか、おびただしい数の生首や殉死者は、権力の集中と大きさをうかがわせるものである。


殷代の青銅器。一面に刻まれたグニャグニャの模様。原型は羊の怪獣なのか、蛇のお化けなのか、逆巻く黄河の水なのか。魑魅魍魎がうじゃうじゃいた当時の人たちの精神世界を表しているようである。神々や悪霊や妖怪が満ち溢れたこの宇宙。

殷の政治の特徴は祭政一致の神権政治。殷王が占いに使ったのが動物の肩甲骨や亀の甲羅。甲骨の亀裂から神意を読み取り吉凶を判断するのが殷王の役割だった。占った結果を甲羅や骨の裏側に刻んで記録した。これが甲骨文字。漢字の原型となる。
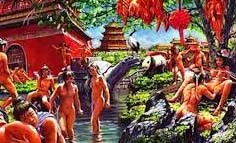
殷の最後の王が紂王(チュウオウ)。絶世の美女と言われた妃・妲己(ダッキ)の虜となり、彼女を喜ばす為に淫蕩な世界に溺れて行った。妲己の為に離宮が造られ、大きな池に酒を満たし、木々には肉が吊るされた。淫らな歌謡が辺りに流れる中、一糸まとわぬ男女が酒の池で戯れ、肉の林で遊ぶ。これが「酒池肉林」。さらに彼女は、人々が本気で殺し合う様を見ては喜び、人民に怨嗟の声が広がると、炮烙(ホウラク)の刑が考え出された。油を塗った柱の上に囚人を上がらせ、下から火を焚きつけるという刑。心ある重臣は王の行状を諌めたが、諫言した者は惨殺され、千肉にされた。
やがて、諫言に寄って捕らえられていた殷王の補佐役・西伯の死後、その息子である周の武王が殷に攻め寄せた。しかし、すでに紂王を見限っていた殷の兵士に戦意はなく、王は宮殿に火を放ち殷王朝は滅んだ。武王は妲己を捕らえて首を刎ね、「殷を滅ぼしたのはこの女だ!」と晒し者にしたという。
実に凄まじい話だが、政権奪取した側がその正当性を示すために前政権の残虐性を脚色することはよくあることだ。『日本書紀』に出てくる第25代・武烈(ブレツ)天皇も凄まじい悪行が並べたてられている。「人の生爪を剥して山芋を掘らせる、人を登らせた木を倒して登った人を殺す、池の樋から人を流して矛で刺殺する、人を木に登らせて弓で射殺する、女性を裸にして目の前で馬の交尾を見せる」。
この武烈の後に、応神天皇5世の孫として越前から入ったのが継体天皇である。王朝交替の歴史観が現れているとの説もある。この「酒池肉林」コード、いかに読み解くべきなのか。
2018年02月10日
人面魚身の正体
とりあえずの中国史・その1

紀元前5000年頃、中国の黄河中流域で文明が誕生した。その前半を仰韶(ヤンシャオ)文化、後半を竜山(ロンシャン)文化という。仰韶文化で使用されていた土器は彩陶、竜山文化で使用されていた土器は黒陶と呼ばれている。
近年、長江流域にも仰韶文化と同時期の遺跡群が見つかっている。稲作の跡や巨大集落遺跡なども発見されており、従来の黄河文明とあわせて中国文明と呼ばれるようになっている。

黄河中流域、半坡(ハンパ)遺跡から出土した彩陶(彩文土器)。川の神のような人面魚身が描かれている。
中国の伝説に堯(ギョウ)・舜(シュン)・禹(ウ)という三人の聖王がいる。堯は自分の王位を舜に譲り、舜はその位をやはり治水で頑張った禹に譲った。この三人は血がつながっていないのに位を譲っている。この形式を禅譲(ゼンジョウ)と言い、理想の王位継承パターンとされる。
禹には、一年中黄河に浸かって働いたために下半身が腐ってしまったという伝承がある。禹王の父親は鯀(コン)。黄河の治水に失敗するのだが、子の禹がそれを成功させたという。人面魚身はまさに「鯀」そのもの。そして禹をも意味していたのだろう。黄河の治水こそ権力の源泉そのものだった。
禹は自分の子に王位を譲ったため、禹から中国最初の王朝ができたとされる。これが司馬遷『史記』に出てくる夏王朝。幻の王朝と言われていた。下の地図は、その領域(B.C.2050頃)を示している。

B.C.1600年頃、夏王朝18代目の王・桀(ケツ)。暴虐無道・財物の浪費。人を馬の代わりにし、その背にまたがって歩き、自分を太陽になぞらえたという。商部族首領の成湯(セイトウ)が挙兵、桀を追放し夏王朝は滅亡したと『史記』は語っている。

紀元前5000年頃、中国の黄河中流域で文明が誕生した。その前半を仰韶(ヤンシャオ)文化、後半を竜山(ロンシャン)文化という。仰韶文化で使用されていた土器は彩陶、竜山文化で使用されていた土器は黒陶と呼ばれている。
近年、長江流域にも仰韶文化と同時期の遺跡群が見つかっている。稲作の跡や巨大集落遺跡なども発見されており、従来の黄河文明とあわせて中国文明と呼ばれるようになっている。

黄河中流域、半坡(ハンパ)遺跡から出土した彩陶(彩文土器)。川の神のような人面魚身が描かれている。
中国の伝説に堯(ギョウ)・舜(シュン)・禹(ウ)という三人の聖王がいる。堯は自分の王位を舜に譲り、舜はその位をやはり治水で頑張った禹に譲った。この三人は血がつながっていないのに位を譲っている。この形式を禅譲(ゼンジョウ)と言い、理想の王位継承パターンとされる。
禹には、一年中黄河に浸かって働いたために下半身が腐ってしまったという伝承がある。禹王の父親は鯀(コン)。黄河の治水に失敗するのだが、子の禹がそれを成功させたという。人面魚身はまさに「鯀」そのもの。そして禹をも意味していたのだろう。黄河の治水こそ権力の源泉そのものだった。
禹は自分の子に王位を譲ったため、禹から中国最初の王朝ができたとされる。これが司馬遷『史記』に出てくる夏王朝。幻の王朝と言われていた。下の地図は、その領域(B.C.2050頃)を示している。

B.C.1600年頃、夏王朝18代目の王・桀(ケツ)。暴虐無道・財物の浪費。人を馬の代わりにし、その背にまたがって歩き、自分を太陽になぞらえたという。商部族首領の成湯(セイトウ)が挙兵、桀を追放し夏王朝は滅亡したと『史記』は語っている。

